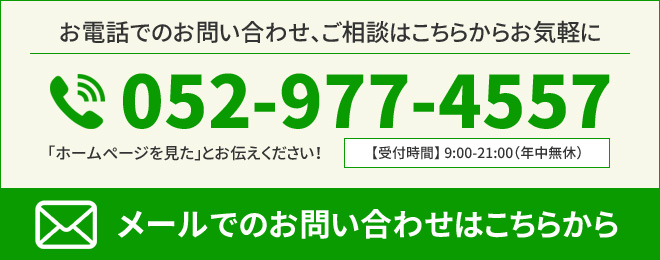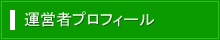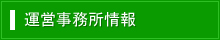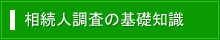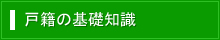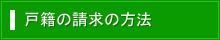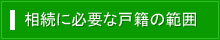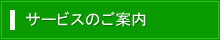トップページ > 戸籍の請求方法(郵送申請の場合)
戸籍の請求方法(郵送申請の場合)
本籍地が遠方にある場合や、平日に役所へ行く時間が取れない場合、郵送で戸籍を請求することができます。
郵送で請求する際には、以下の書類を準備して、本籍地の市区町村役場の戸籍担当係宛に送付してください。
【必要な書類一覧】
- 戸籍交付申請書
- 定額小為替(戸籍交付手数料分)
- 本人確認書類のコピー(例:運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 切手を貼った返信用封筒
- 関係が確認できる書類(請求内容により異なります)
- 委任状(代理人が請求する場合のみ)
- 代理人の本人確認書類のコピー(代理人が請求する場合のみ)
戸籍交付申請書について
戸籍交付申請書は、各市区町村役場のホームページからダウンロードできます。
もし申請書が見つからない場合や、プリンターがない場合は、自作の申請書でも対応してもらえます。便せん等に「戸籍交付申請書」と記入し、次の項目を記入してください。
- 1. 本籍地と筆頭者(※1)
- 2. 戸籍の種類と必要な通数
- 3. 必要な方の氏名と生年月日
- 4. 使用目的・請求理由(※2)
- 5. 申請者の住所、氏名、生年月日
- 6. 日中連絡可能な電話番号(携帯電話でもOK)
- 7. 申請者と必要な方との続柄
「本籍地と筆頭者」について
本籍地や筆頭者に誤りがあると交付してもらせません。正確な本籍地と筆頭者をご記入ください。不明な場合は、本籍地の記載がある住民票の写しを取得して確認できます。
「使用目的・請求理由」について
傍系親族(兄弟姉妹や、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍を請求する際には、正当な理由を詳しく記載する必要があります。
記載例
「請求者○○は、令和○年○月○日に死亡した○○の相続人であるが、○○法務局への相続登記の申請の添付資料として相続人○○が記載されている戸籍を提出する必要がある。」のように、戸籍が必要な理由や提出先を記載してください。
交付手数料について
戸籍の交付手数料は、おおむね全国一律で定められています。
| 戸籍の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 1通 450円 |
| 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) | 1通 450円 |
| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 1通 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
郵便請求の場合、手数料の支払いには定額小為替(ていがくこがわせ)を使用します。切手や収入印紙では受け付けられませんのでご注意ください。
また、相続手続きのために戸籍を請求する際は、複数の交付が必要になる場合があります。念のため、3~4通分の定額小為替を入れておくと安心です。
定額小為替について詳しくは下記リンク先をご覧ください。
本人確認書類のコピーについて
戸籍を請求する際には、法令により申請者の本人確認が求められます。
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されたもの)などのコピーを同封してください。
上記の身分証明書をお持ちでない場合、事前に請求先の役所にご相談ください。健康保険証や年金手帳などの証明書でも本人確認が可能です。
なお、代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
返信用封筒について
返信用封筒には、申請者の現住所と氏名を記入し、あらかじめ切手を貼り付けた上で同封してください。
なお、返送先は本人確認書類と申請書に記載された住所に限定されます。別の住所宛では交付されませんのでご注意ください。
なお、郵便料金は、封筒のサイズと重量によって異なります。
| 内容 | 重量 | 料金 |
|---|---|---|
| 定形郵便物 | 50gまで | 110円 |
| 定形外郵便物 | 50gまで | 140円 |
| 100gまで | 180円 | |
| 150gまで | 270円 |
定形郵便物として送れるサイズは縦23.5cm、横12cm、厚さ1cmまでですので、長形3号までの封筒なら定形郵便物で送れます。
重量の目安としては、50g以内で納まる枚数としては、A4(戸籍のサイズ)なら8枚程度、戸籍の通数で考えると2~3通程度になります。重量オーバーになる場合も考え、余分に切手を同封しておくと安心です。
交付される通数が多い場合や、戸籍が折れないように返送してほしい場合は、角2サイズの封筒がおすすめです(料金は定形外郵便物の料金になります)。
お急ぎの方は速達(250gまでは1回300円が基本料金に加算)をご利用ください。最短で請求日から3日ほどで届くことがあります(普通郵便は、土日曜・祝日に配達がないため、平均7日前後かかります)。
返信用封筒の代わりにレターパックを使用することもできます。レターパックライト(1通430円)の場合、重量が4kgまで、厚さ3cm以内まで送れ、土日曜・祝日にも配達されますし、配達速度は速達並みです。
関係が確認できる書類について
戸籍を請求できるのは、原則として以下の方々に限られます。
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 直系尊属(例:父母、祖父母など)
- 直系卑属(例:子、孫など)
請求する戸籍に申請者が記載されていない場合や、申請を受けた市区町村にある戸籍で申請者と関係が確認できない場合は、親族関係が分かる戸籍のコピーを添付してください。
なお、傍系親族(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍を請求するには、正当な理由とともに関係が確認できる戸籍のコピーの添付が必要になります。
【正当な理由の例】
- 相続人を特定するために戸籍の内容を確認する必要がある場合
- 遺産分割調停の申立てに際し、家庭裁判所へ戸籍を提出する場合
- 相続税の申告に際し、税務署へ戸籍を提出する場合
- 公正証書遺言を作成するために戸籍を公証役場に提出する場合
【関係が確認できる戸籍の一例】
- 申請者(相続人)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍
上記は一例です。代襲相続が発生していると、申請者の亡父(または亡母)の出生から死亡までの戸籍や、被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要になる場合もあります。
相続に必要な戸籍に関するお役立ちページ