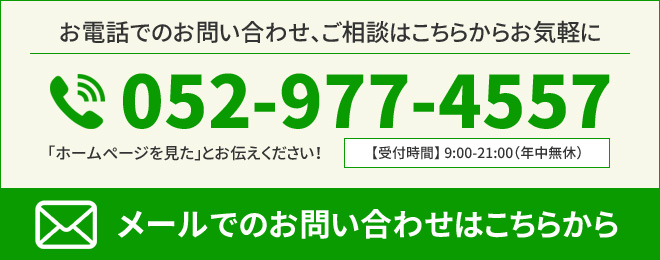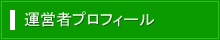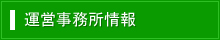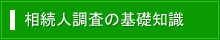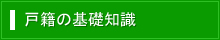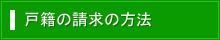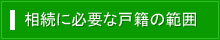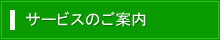トップページ > 古い戸籍を見るポイント
古い戸籍を見るポイント
戸籍は、法改正により今までに何度か作り直されてきました。これを「戸籍の改製」といいます。
最近では平成6年に改製がおこなわれ、それ以前では昭和23年、大正4年、明治31年、明治19年に改製がおこなわれました。
相続の手続きでは昔の戸籍が必要になるのですが、戸籍が改製されたことで、それぞれの時代の戸籍の特徴や確認すべきポイントが異なります。
特に、以下の2つの違いに注目しましょう。
- 戸籍のコンピュータ化
- 「家」単位から「夫婦」単位の戸籍へ
戸籍のコンピュータ化について
平成6年の法改正により、戸籍の管理がコンピュータ化されました。
これに伴い、戸籍の名称や表記形式が変更されています。
- 【名称の変更】
-
- 戸籍謄本 → 戸籍全部事項証明書
- 戸籍抄本 → 戸籍個人事項証明書
- 【表記の変更】
-
- 縦書き → 横書き
- 文章形式 → 項目形式
これらの変更により、今までよりも戸籍の情報がより見やすく、分かりやすい形になりました。
【コンピュータ化後の戸籍(戸籍全部事項証明書)】
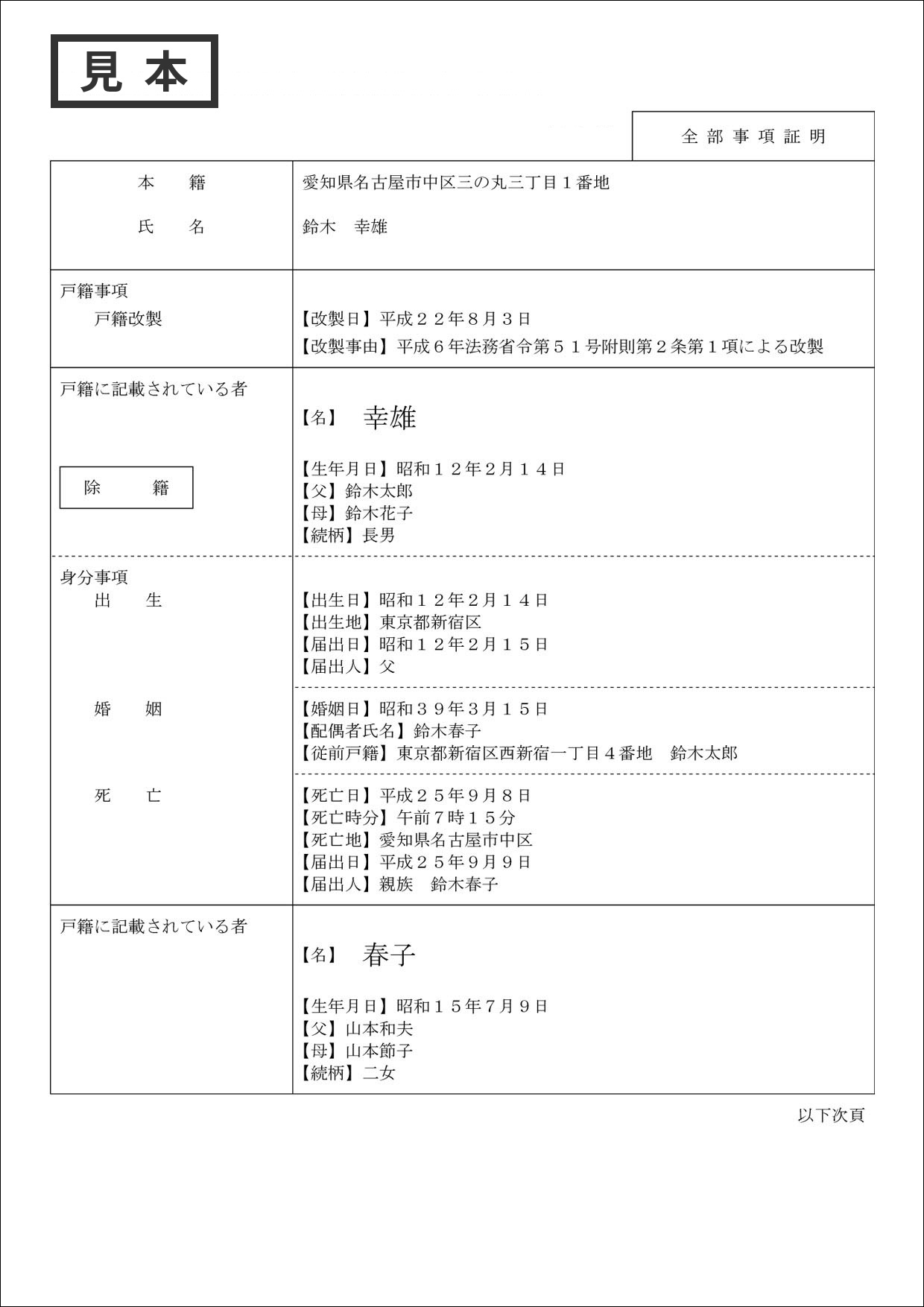
【コンピュータ化前の戸籍(改製原戸籍謄本)】
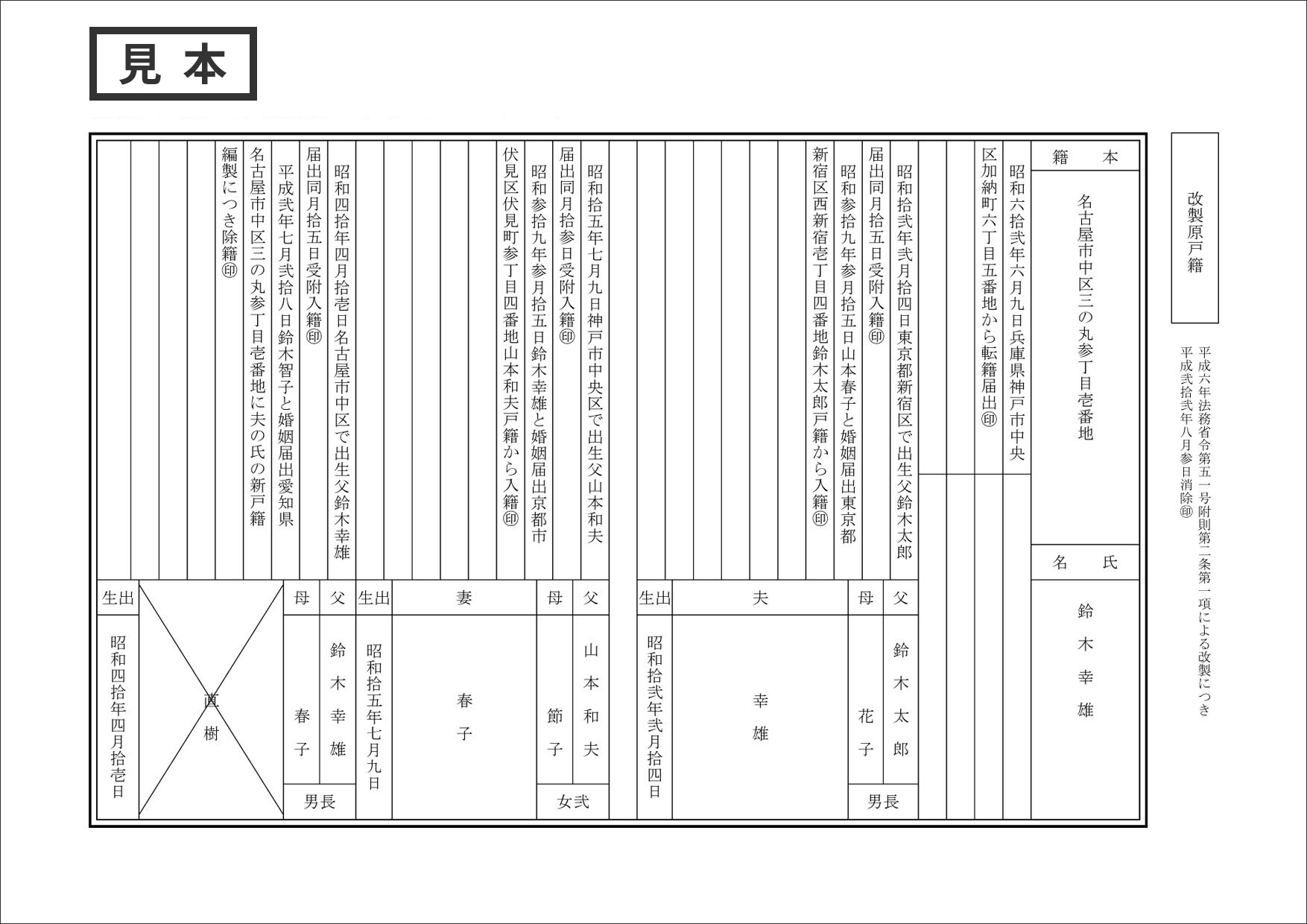
戸籍の仕組みは時代とともに変化しています
昔の戸籍は「家」単位で作られていて、戸主(家長、家の代表者)を中心に、子やその配偶者、孫、兄弟姉妹やその配偶者、甥姪などが同じ戸籍に記録されていました。
しかし、昭和22年の民法改正により戸主制度は廃止され、「戸主」から「筆頭者」になり、戸籍は「家」単位から「夫婦」単位へ移行しました。
そのため、現在の「夫婦」単位の戸籍と比べ、昔の戸籍には記載されている人数が非常に多く、相続関係を理解するのが難しくなることがあります。
また、戸籍の内容自体はどの時代もほぼ共通ですが、戸籍事項欄については時代ごとに違いがあります
- 昭和23年式・平成6年式戸籍には戸籍事項欄が設けられています。
- 大正4年式戸籍では、戸主の事項欄に戸籍事項が記録されていました。
- 明治31年式戸籍には「戸主となりたる原因及び年月日」欄がありました。
戸籍を確認するときは、それぞれの時代の制度の違いを意識して読み解くことが大切です。
相続に必要な戸籍に関するお役立ちページ
戸籍の基礎知識
戸籍の請求方法について
相続人様向けサービス